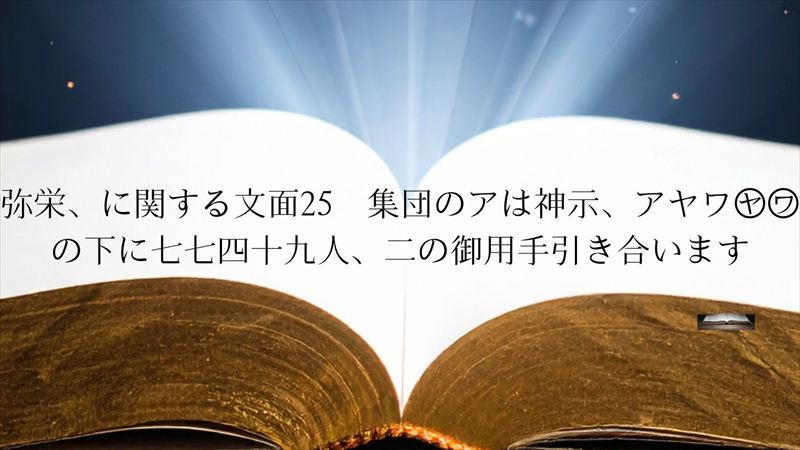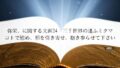弥栄、に関する文面25に進みます。
今回は、〇つりの巻(マツリの巻)の文面2つです。
1つの文面は、第十五帖、旧九月八日から当分の礼拝に仕方ついての文面ですが、こちらは、変化がないと見てゐます。ですが、覚悟が決まった方は、旧九月八日から礼拝を始めて下さい。
2つ目の文面、第十七帖は、全面的マンデラ・エフェクト、を起こしてゐます。
ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、が元の下に七人と七人、四十九名の仕組みについて。
それも、集団のアは神示、と伝えられています。
これは初めて、と見ます。
更には、その集ひは、二の御用手引き合って、天晴れやりて下されよ、
という集団(つどひ)が、御用手引き合う関係となってきている事。
また、今度の御用は、一つの分れの御用である事。
ミタマのしょうらい、段々判りて来るのは、生来(過去)、将来(未来)どちらも判るようになる事。
万民ミタマまつりの御用からかかりて呉れよ、
の段階に入っており、ミタマは、今回の文面からは、三・、が気になっています。
三界和合です。
最後は、うつし世のそれの御用、結構ひらけ輝くぞ。
とまで伝えられています。
まつりの巻でも、遂に、七七四十九の仕組みの詳細から、一つの分かれの御用について、しょうらい(過去)(未来)両方判るようになる事。万民ミタマまつりの御用が始まりつつある事。まで伝えられ始めました。
愈々の世が始まりますよね。
それでは、まつりの巻の2つの文面をお伝えします。
- 1.〇つりの巻(マツリの巻)第十五帖 旧九月八日からの当分の礼拝の仕方です。覚悟が決まった方から礼拝を始めて下さい。
- 2.〇つりの巻(マツリの巻) 第十七帖 アヤワ㋳㋻の下に七人と七人、四十九人の仕組み、二の御用手引き合う仕組みです。
- Ⅰ.集団のアは神示、ヤとワは左、右、㋳と㋻はその補(たすけ)であり、またヤの補が㋻、ワの補が㋳、でもあります。元は、ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、です。
- Ⅱ.ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、が元の下に七人と七人です。正と副、その下に四十九人の流れとなります。
- Ⅲ.二の御用手引き合って、天晴れやりて下されよ、としてください。七七四十九人の集団(まどい)つくってよいです。
- Ⅳ.強く踏み出してください。くどいですが、百十(もと)はそのままです。
- Ⅴ.今度の御用は、一つの分れの御用です。神示よく(四九)読んで下さい。
- Ⅵ.ミタマのしょうらい、段々判りて来るぞ、とあります。生来、将来どちらも判るようになります。
- Ⅶ.万民、ミタマまつりの御用からかかりて呉れよ(九〇四)としてください。うつし世のそれの御用、結構ひらけ輝きます。
- 3.まとめ
1.〇つりの巻(マツリの巻)第十五帖 旧九月八日からの当分の礼拝の仕方です。覚悟が決まった方から礼拝を始めて下さい。
●旧九月八日からの当分の礼拝の仕方 書き知らすぞ、大神様には、先づ神前に向って静座し、しばし目つむり、気しづめ、一揖、一拝二拝八拍手、数歌(かずうた)三回、終りて「ひふみ」三回のりあげ、天(あめ)の日月の大神様、弥栄ましませ、弥栄ましませ、地(くに)の日月の大神様、弥栄ましませ、弥栄ましませとのりあげ、終って「誓の言葉」ちかへよ。終りて神のキ頂けよ、三回でよいぞ、終りて八拍手、一拝、二拝、一揖せよ、次に神々様には一揖、一拝二拝四拍手、数歌三回のりて、百々諸々(もももろもろ)の神様 弥栄ましませ弥栄ましませ、と、宣りあげ、終りて「ちかひの言葉」ちかへよ。終りて四拍手、二拝一揖せよ。霊(タマ)の宮には一揖一拝二拍手、数歌一回、弥栄ましませ弥栄ましませと宣り、二拍手、一拝一揖せよ、各々の霊様(おのもおのもみたま)には後で「ミタマのりと」するもよいぞ。
この文面は、今回は、変わっていないと見ます。
私が4年前から始めた礼拝時と同じと見ます。
大神様には、一揖、一拝二拝八拍手、数歌(かずうた)三回、終りて「ひふみ」三回、
その後、大神様を読み上げます。
その後、弥栄(やさか)ましませ、弥栄(いやさか)ましませ、
とのりあげ、その後、誓の言葉を読んで下さい。
誓の言葉は、まつりの巻、第三帖にあります。
参考:弥栄、に関する文面24 三千世界の迷ふミタマ、コトで慰め、邪を引き寄せ、抱き参らせて下さい
その後、終わりて神のキを三回頂き、終りて八拍手、一拝、二拝、一揖、します。
神のキの頂き方は、アメの巻第十五帖にあります。
続いて、神々様には、一揖、一拝二拝四拍手、数歌三回のりて、百々諸々(もももろもろ)の神様 弥栄ましませ弥栄ましませ、と礼拝します。
その後、ちかひの言葉を読み上げますが、神々様に向けての誓は、二十帖にあります。
終りて四拍手、二拝一揖します。
その後、霊(タマ)の宮には一揖一拝二拍手、数歌一回、弥栄ましませ弥栄ましませと宣り、二拍手、一拝一揖します。
各々の霊様(おのもおのもみたま)には後で「ミタマのりと」するもよいぞ。
とありますが、これは、水の巻、第三帖、御先祖様の拝詞、がそれにあたると見ます。
まず、旧九月八日からの礼拝、は、このように進めて頂ければ、と思います。
覚悟が決まった方から、進めて下さい。
繰り返しですが、大峠を越すには、この道が一番楽に進みます。
遅れる程に苦しみますので、早う進めて下さい。
2.〇つりの巻(マツリの巻) 第十七帖 アヤワ㋳㋻の下に七人と七人、四十九人の仕組み、二の御用手引き合う仕組みです。
Ⅰ.集団のアは神示、ヤとワは左、右、㋳と㋻はその補(たすけ)であり、またヤの補が㋻、ワの補が㋳、でもあります。元は、ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、です。
●集団(まどゐ)のアは神示ぢゃ、ヤとワとは左と右ぢゃ、教左と教右じゃ、㋳と㋻はその補(たすけ)ぢゃ、教左補、教右補ぢゃ、ヤの補(たすけ)は㋻ぢゃ、ワの補(たすけ)は㋳ぢゃ、ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、が元ぢゃ、
こちらも文面が少し変わった、と見ます。
集団(まどゐ)のアは神示ぢゃ、とあります。
元の元です。永劫の過去です。・です。
この表現は初めて、と見ます。
ヤとワは、その左と右です。教左と教右、です。
㋳と㋻は、その補(たすけ)となります。
教左補が㋳、教右補が㋻、です。
また、更にですが、
ヤの補(たすけ)は㋻、
ワの補(たすけ)は㋳、
でもあります。
ですから、ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、が元です。
Ⅱ.ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、が元の下に七人と七人です。正と副、その下に四十九人の流れとなります。
●その下に七人と七人ぢゃ、正と副ぢゃ、その下に四十九人ぢゃ、判りたか、集団(まどい)弥栄々々。
その下に七人と七人です。正と副で、その下に四十九人です。
これは、御自身が、アヤワ㋳㋻となった下に、七人と七人となるのですね。
集団(まどい)弥栄々々、となります。
Ⅲ.二の御用手引き合って、天晴れやりて下されよ、としてください。七七四十九人の集団(まどい)つくってよいです。
●皆御苦労ながら二の御用手引き合って、天晴れやりて下されよ、集団(まどい)つくってよいぞ。
七七、四十九人の仕組みを作っていきますと、皆御苦労となり、二(つぎ)の御用手引き会って、天晴れやりて下されよ、とあります。
この四十九人の集団(まどい)は、二の御用を手引き合う、ところが一つ鍵となっています。
集団(まどい)つくってはならない一方で、此の道に進みますと、集団(まどい)作る流れとなります。
神のハタラキは、順が大切です。
Ⅳ.強く踏み出してください。くどいですが、百十(もと)はそのままです。
●強くふみ出せよ、くどい様なれど百十(もと)はそのままぢゃぞ。
強くふみ出せよ、とあります。
くどい様なれど、百十(もと)はそのまま、となります。
Ⅴ.今度の御用は、一つの分れの御用です。神示よく(四九)読んで下さい。
●今度の御用は一つの分れの御用ぢゃぞ、神示よく読むのぢゃぞ、
この文面も初めてですね。
今度の御用は、一つの分れの御用です。
元(百十)はそのまま、二(つぎ)の御用となり、分かれていく仕組みです。
そのヒントは、御神示にありますので、神示よく(四九)読めよ、とあります。
しきまきや、くにつつみ、から生み出して読めよ、というのもあるでしょうし、
それを、ア、から生み出すのです。
Ⅵ.ミタマのしょうらい、段々判りて来るぞ、とあります。生来、将来どちらも判るようになります。
●身魂のしょうらい段々判りて来るぞ、
この事でミタマのしょうらい(生来)(将来)段々判りて来ます。
ここは、以前、確か、生来、だったはずです。
生れてきた過去、が判りて来る、だけでしたが、ひらがな、のマンデラ・エフェクトによって、
ミタマの未来までも判ってくる、という段階になってきています。
過去を理解し、そして、思念を変えていく行から、未来まで判る境地になってきます。
また、来る未来とは、過去の状況でもあり、ですから、前世ヒーリングで改心していく事。
それが、来る未来を生み出す事が判ってきます。
(同時に、過去のマンデラ・エフェクトまで起こす事もあります。)
Ⅶ.万民、ミタマまつりの御用からかかりて呉れよ(九〇四)としてください。うつし世のそれの御用、結構ひらけ輝きます。
●万民ミタマまつりの御用からかかりて呉れよ、うつし世のそれの御用、結構ひらけ輝くぞ。
万民ミタマまつり、という単語、また、うつし世のそれの御用、という文面も初めてです。
万民ミタマまつりの御用からかかりて呉れよ(九〇四)としてください。
ミタマ、身魂、三・、三㊉真。
ミタマのまつり方は様々あります。
それには、くにつつみ、しきまきや、から生み出す事が求められます。
それを、世にうつす、それ(そ、〇)(五三体の大神様を生み出す)の御用、結構ひらけ輝きます。
3.まとめ
旧九月八日からの当分の礼拝につきましては、覚悟が決まった方から礼拝を始めて下さい。
集団のアは神示、ヤとワは左、右、㋳と㋻はその補(たすけ)であり、またヤの補が㋻、ワの補が㋳、でもあります。
元は、ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、です。
ア、ヤ、ワ、㋳、㋻、が元の下に七人と七人です。正と副、その下に四十九人の流れとなります。
二の御用手引き合って、天晴れやりて下されよ、としてください。
七七四十九人の集団(まどい)つくってよいです。
強く踏み出してください。
くどいですが、百十(もと)はそのままです。
今度の御用は、一つの分れの御用です。神示よく(四九)読んで下さい。
しきまきや、くにつつみ、から生み出し読んで下さい。
ミタマのしょうらい、段々判りて来るぞ、とあります。
生来、将来どちらも判るようになります。
万民、ミタマまつりの御用からかかりて呉れよ(九〇四)としてください。
うつし世のそれの御用、結構ひらけ輝きます。
修業守護の神々様、役員守護の神々様、天の日月の大神様、五柱十柱の神々様、地の日月の大神様、世の元からの生き神様、百々諸々の神々様、いつも御守護頂き、ありがとうございます。